太陽光発電の今後は2050年に国内発電量の36%を占める見通し で、将来性は明るいといえます。売電価格下落や2030年問題の課題と水上太陽光発電など、5つの打開策を解説します。
太陽光発電の今後について「もう遅い」「厳しい」といった声を耳にすることがあります。確かに売電価格の下落や出力抑制の増加など、事業者が直面する課題は少なくありません。しかし、技術革新や新たな活用方法により、太陽光発電には依然として将来性があります。
本記事では、太陽光発電事業の現状と課題を整理し、収益性を確保するための具体的な打開策を紹介します。
国内の太陽光発電ビジネスの現状
太陽光発電の今後を考える前に、まず国内の現状を正確に把握しておきましょう。
総発電量に占める太陽光発電の割合
日本の太陽光発電は着実に成長を続けています。
資源エネルギー庁のデータによると、2023年度の太陽光発電による発電電力量は965億kWhに達し、日本全体の発電電力量の9.8%を占めるまでになりました 。これは主要電力源としての地位を確立していることを示しています。
国際的に見ても、日本の総発電量に占める太陽光発電の割合は8.3%となっており、ドイツの8.5%、スペインの8.0%と並んで世界トップクラスの水準です。中国やアメリカは絶対的な発電量では日本を大きく上回りますが、総発電量に占める割合はそれぞれ4.0%、3.4% と日本より低く、日本の太陽光発電普及率の高さがわかります。
出典:資源エネルギー庁「今後の再生可能エネルギー政策について(2025年6月3日)」
面積あたりの太陽光設備容量
より注目すべきは、限られた国土での導入実績です。
経済産業省の調査によると、日本の国土面積あたりの太陽光導入容量は175kW/㎢と、主要国のなかで世界第1位となっています。平地面積でみると、2位のドイツの約2倍という驚異的な数値です。
平地面積で見るとその差はさらに顕著で、日本は426kW/㎢と、184kW/㎢のドイツの2倍以上の密度で太陽光発電を導入しています。これは、日本が限られた土地を最大限活用して太陽光発電を 普及させてきた結果です。
出典:経済産業省「今後の再生可能エネルギー政策について」

太陽光発電の導入費推移
技術革新により、太陽光発電の導入コストは年々低下しています。
固定価格買取制度(FIT)認定を受けた太陽光発電の導入費は、2013年に1kWあたり37万円だったものが、2023年には28万円まで下がりました。これは約24%の費用削減を意味します。
とくに太陽光パネル自体のコストは45%も低下しており、技術の進歩と量産効果が導入コストの大幅な削減につながっています。
なお、FIT制度は継続しているものの、新規導入の中心はFIP制度へと移行しつつあります。
資源エネルギー庁「再エネを日本の主力エネルギーに!「FIP制度」が2022年4月スタート」
売電価格の推移
一方で、FIT制度による売電価格は、制度開始以来下落傾向が続いています。産業用太陽光発電(10kW以上)の場合、2012年度の制度開始時は40円/kWhでしたが、2024年度には10kW以上50kW未満で10円/kWh、50kW以上で9.2円/kWhまで下落 しました。
ただし、この売電価格の下落は導入コストの低下に連動しているため、事業そのものの価値がなくなったわけではありません。
経済産業省は、太陽光発電の発電コスト(LCOE)が2024年度時点で1kWhあたり12円、2035年度には7.5〜8円台まで低下する見通し を示しています。これは、ほかの発電方法と比べても十分に競争力がある水準です。
出典:資源エネルギー庁「買取価格・期間等(2012年度~2024年度)」
出典:経済産業省「太陽光発電の現状と自立化・主力化に向けたチャレンジ」
太陽光発電ビジネスが抱える今後の課題
現在の太陽光発電ビジネスには、確実に対処すべき課題が存在します。これらを正しく理解し、しっかりと対策をとることが、今後も事業を続けていくための大切なポイントです。
出力抑制の増加
太陽光発電ビジネスで大きな課題のひとつとなっているのが「出力抑制」です。これは、電力の需要と供給のバランスを保つため、電力の供給(発電量)を一時的に減らすこと、あるいは停止することです。
2022年度には6社だった出力抑制実施事業者が、2023年度には9社に拡大しました。これは太陽光発電の導入量増加にともなう必然的な現象ですが、事業者にとっては売電収入の減少に直結します。
FIT制度で売電している事業者は出力抑制の要請に従う義務があるため、当初のシミュレーションどおりの収益を得られないリスクが高まっています。
出力抑制はとくに電力需要が少ない時期(年末年始、ゴールデンウィークなど)や好天が続く日に実施されやすく、売電収入への影響を事前に正確に予測することは困難です。
売電から自家消費へのシフト
売電価格の下落と電気料金の高騰により、太陽光発電の活用方法は売電から自家消費へとシフトしています。
とくに、ロシアのウクライナ侵攻による国際的なエネルギー価格高騰の影響で、日本の電気料金も上昇を続けているため、自家消費による電気代の節約効果に注目が集まっています。
ただし、自家消費をフルに活用するには蓄電池を導入する必要があるケースが多く、その分の初期費用がかかります。また「電気を使う時間帯」と「発電する時間帯」をうまく合わせる工夫も必要になるため、従来の売電とは異なる事業運営が必要です。
2030年問題:寿命を迎えたパネルの廃棄
「2030年問題」とは、FIT制度開始当初に導入された太陽光発電設備が寿命を迎え、大量廃棄のピークに達する見込みを指します。NEDOの調査では、2034~2036年の間に22~34万トンの発電設備が廃棄されると推計されています。
とくに懸念される問題は「不法投棄」です。太陽光パネルには種類によって鉛・セレン・カドミウムなどの有害物質が含まれており、適切に処理されなければ環境汚染を引き起こす可能性があります。
さらに、産業廃棄物として処分する費用は高く、2012年度導入設備で1kWあたり約1.7万円となるため、処分コストを避けようとして不法投棄されるケースが懸念されています。
この問題に対応するため、2022年7月から産業用の太陽光発電事業者には廃棄費用の積立が義務づけられました。また、リサイクルや再利用の技術開発も進められています。
事業者にとっては追加のコスト負担となりますが、持続可能な事業運営のためには避けて通れない課題です。
出典:国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)「太陽光発電開発戦略2025について」
設置に適した用地の制約
日本は国土が狭く、すでに平地に設置された太陽光発電の量は世界でもトップクラスです。そのため、新しい設置場所を見つけるのが大きな課題になっています。
これまでの急激な導入拡大によって、条件のよい土地はほぼ開発済みとなっており、今後の大規模開発には限界があります。
また、過剰な土地開発による土砂災害リスクや景観破壊も問題視されており、地域住民の理解を得にくいケースも増えています。こうした背景から、従来の平地での大規模開発に代わる新たな 設置手法を早急に確立する必要があります。
こうした用地不足の課題に対する革新的な解決策として「水上太陽光発電」が注目を集めています。ため池、貯水池、ダム湖などの水面を活用することで、陸地を消費せずに大規模な発電施設を設置できます。
シエル・テール・ジャパンは、水上太陽光発電のパイオニアとして、世界初の水上太陽光用架台システムを展開しました。日本のみならず世界各地での実績を誇り、環境負荷だけでなく、安全性にも考慮したフロート作りとアンカー設計を行っています。

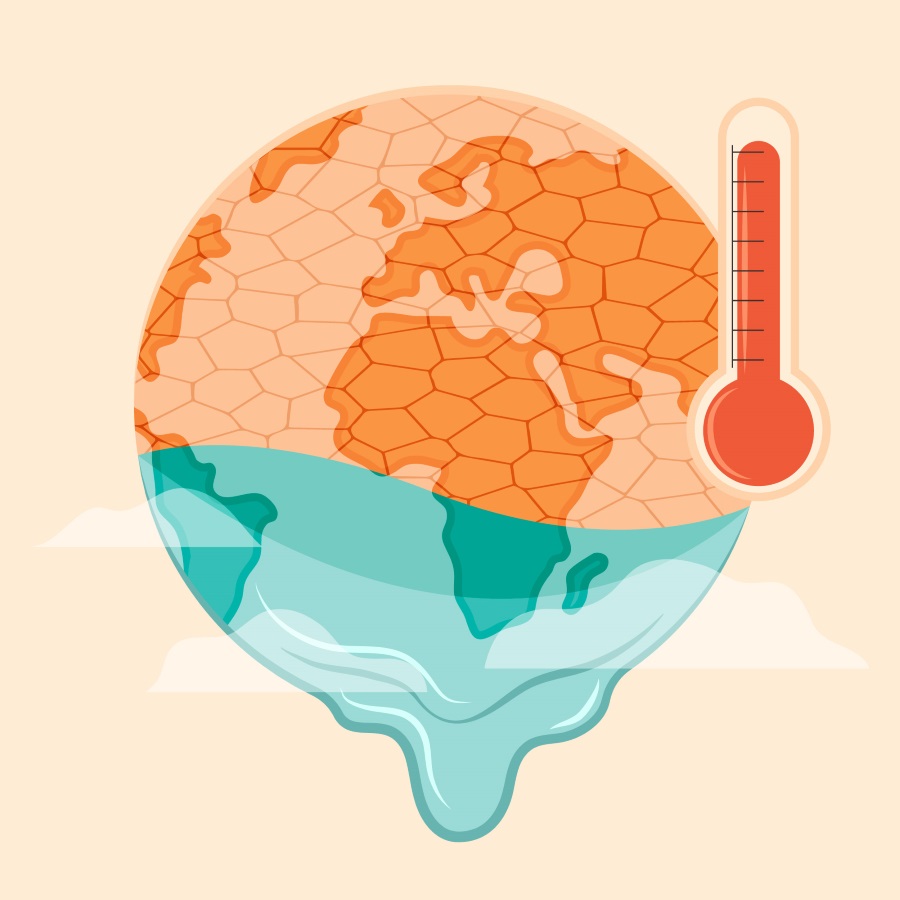
Photo designed by Freepik
自然災害への対策
日本は台風や地震などの自然災害が多い国であり、太陽光発電設備はこれらの災害によって破損するリスクを常に抱えています。
さらに近年の気候変動により、従来想定していた以上の強風や豪雨に見舞われるケースが増加しており、設備の耐久性向上と適切な保険の確保が重要になっています。
とくに大規模な産業用設備の場合、一度の災害で数億円規模の損害が発生する可能性があり、事業継続に深刻な影響を与えかねません。設計・施工段階から災害リスクを十分考慮した対策を講じることが不可欠です。
課題はあるけれど…太陽光発電には将来性があると言える理由
さまざまな課題が存在する一方で、太陽光発電には確実に将来性があります。これは単なる希望的観測ではなく、国策、技術革新、経済合理性、社会的要請という多角的な根拠にもとづいた判断です。
再生可能エネルギーの導入を国が推進している
日本政府は2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする「カーボンニュートラル」を宣言しており、その実現には再生可能エネルギーの拡大が欠かせず、太陽光発電の導入を推進しています。
この目標はパリ協定やSDGsといった国際的な取り組みとも密接に連動しており、後退することはありません。政府や地方自治体による補助金制度も継続的に整備されており、太陽光発電の導入を後押ししています。
また、2022年4月にスタートしたFIP制度(Feed-in Premium)により、 太陽光発電事業者は市場価格に応じた収益を確保できる仕組みが整いました。
従来のFIT制度では、発電した電力を一定の価格で長期間買い取ってもらえるため、収益が安定する一方で、市場価格が高騰してもその恩恵を受けにくいという課題がありました。
一方、FIP制度では、発電した電力を市場(卸電力取引所など)に販売し、その市場価格に加えて「一定のプレミアム(補助額)」が上乗せされます。これにより、事業者は市場価格が高いときにはより高い収益を得られ、低いときにもプレミアムによって最低限の収益が確保される仕組みになっています。
出典:資源エネルギー庁「第2節 諸外国における脱炭素化の動向」
こちらの記事 では、FIP制度について解説しています。
FIP制度の仕組みや収益構造も取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。
技術進歩により発電効率がアップしている
太陽光発電の技術は年々進歩しており、発電効率も継続的に向上しています。
太陽光パネルのモジュール変換効率は、2013年の16%から2020年には22%に上昇し、2030年には25%まで向上する見込み です。この技術進歩により、同じ規模の発電所でもより多くの電気を生み出せるようになっています。
さらに注目すべきは、シャープが変換効率約34%の太陽光パネル開発に成功 したことです。パワーコンディショナーの変換効率も96.5%程度まで向上 しており、システム全体の発電効率は着実に改善されています。
これらの技術革新により、初期投資に対する発電量が増加し、事業収益性の向上が期待できます。
電気料金の削減に役立つ
国際情勢が不安定な影響で、日本の電気代は上がり続けています。
とくにロシアのウクライナ侵攻によるエネルギー価格の高騰は、化石燃料に大きく頼っている日本の電力システムに強く影響しています。
こうした状況のなかで、太陽光発電による自家消費は電気料金削減の有効な手段となっています。とくに法人の場合、電気料金は事業コストの大きな部分を占めるため、太陽光発電による削減効果は利益の改善に直結します。
さらに、自家消費した電気は燃料費調整額の影響を受けないため、電気代の変動リスクを抑え、エネルギーコストを安定させる効果もあります。

Photo designed by Freepik

セカンダリー市場への注目が高まっている
FIT制度の見直しや売電価格の下落にともない、中古の太陽光発電設備を売買する「セカンダリー市場」が活発になってきています。
中古設備には早期の収益化、初期費用の抑制、高い固定買取価格の引き継ぎ、自家消費要件の回避といったメリットがあり、投資家からの関心が高まっています。
また、事業継続だけでなく、適切なタイミングでの売却による資金回収も可能になり、投資の柔軟性が向上しています。 こうした点からも、太陽光発電は今後も有望な投資対象として期待されているのです。
ESG経営が求められるようになっている
企業を取り巻く環境変化により、環境・社会・企業統治に配慮した「ESG経営」への要請が高まっています。とくに脱炭素社会の実現に向けて、企業には積極的な環境対策が求められており、太陽光発電の導入はそのもっとも効果的な手段のひとつです。
太陽光発電を導入することでCO2削減に貢献し、企業としての社会的責任を果たすことにつながります。さらに、投資家や金融機関からの評価が上がり、企業価値や資金調達力の向上、ブランドイメージの改善といった多くのメリットも期待できます。
ESGへの取り組みはもはや選択肢ではなく、企業経営における必須要件となっており、 太陽光発電の需要は今後も着実に増えていくと考えられます。

太陽光発電に今後期待される未来
太陽光発電は、単に電気をつくるための手段にとどまらず、社会全体の持続可能な発展を支える大切なインフラへと進化していきます。長期的な視野で見ると、その社会的意義はさらに拡大していくでしょう。
2050年カーボンニュートラルの実現
2050年カーボンニュートラルは、日本を含む世界各国が掲げる重要な目標であり、太陽光発電はその実現に不可欠な要素です。
自然エネルギー財団の推計によると、2050年の日本の太陽光発電による発電電力量は4,370億kWhまで拡大し、国全体の発電電力量の36%を占めて最大の電力供給源になる見通し です。
この見通しでは、太陽光発電市場の長期的な成長ポテンシャルの大きさを示しています。カーボンニュートラル目標の達成は国際公約でもあり、この目標に向けた取り組みは今後さらに加速していくと予想されます。
出典:自然エネルギー財団「太陽光発電の動向 日本と世界の最新データ&トレンド」
こちらの記事 では、カーボンニュートラルと太陽光発電の関係性について解説しています。
具体的な導入方法や経済効果も取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。
エネルギー安全保障の実現
日本は化石燃料がほとんど取れないため、エネルギーの多くを海外から輸入に依存しています。そのため、国際情勢が不安定になると資源の確保が難しくなり、実際にここ数年は世界的なリスクの高まりによって電気代が大きく上がる経験をしてきました。
一方、太陽光発電は国内でつくれる「純国産」のエネルギーです。輸入に頼らずに電気を生み出せるため、エネルギーの安全保障という観点でも大きな価値があります。
太陽光発電の普及拡大により、エネルギー自給率が高まり、海外の状況に左右されにくい安定した電力供給システムを築くことができます。
より高性能な太陽光パネルの開発
現在主流の太陽光パネルには、重量や寸法が大きく設置場所に制約があるという課題があります。この課題を解決する次世代型太陽電池として「ペロブスカイト太陽電池」の開発が進んでいます。
ペロブスカイト太陽電池は軽量で柔軟性があり、従来困難だった場所への設置が可能になると期待されています。印刷技術を応用した製造方法により低コスト化も見込まれており、太陽光発電の適用範囲を大幅に拡大する可能性があります。
ただし、耐久性や発電効率の安定性など、まだ解決すべき課題も多く、実用化までには時間がかかる見通しです。
それでも、こうした技術革新によって、建物の壁や屋根といった従来難しかった場所への設置も現実的になり、太陽光発電市場はさらに拡大していくことが期待されています。

太陽光発電ビジネスの今後の取り組み・活用法
これまで見てきた現状や課題、そして将来性をふまえ、太陽光発電事業者が中長期的に収益性や事業の継続性を守るための具体的な取り組み・活用法を紹介します。
売電先を変更して単価を上げる
近年の売電価格の下落に対しては、売電先を見直すことが有効な収益維持・向上策となります。
電力会社を見直す
FIT期間終了後、売電先を大手電力会社から新電力に変更することで、より高い買取価格を得られる可能性があります。新電力各社は大手電力会社よりも数円高い買取価格を設定しているケースが多く、自社サービスとのセット利用でさらに優遇価格を適用するプランも存在します。
電力自由化により選択肢が拡大しているため、複数の新電力会社の条件を比較検討し、もっとも有利な売電先を選択することが重要です。ただし、新電力会社の経営状況や契約条件も十分確認した上で判断する必要があります。
オフサイトPPAを活用する
オフサイトPPA(Power Purchase Agreement)は、電力会社以外の事業者と個別に電力売買契約を結ぶ仕組みです。一般的な相場は10〜12円/kWhとされており、大手電力会社の買取価格よりも高く売電できる可能性があります。
オフサイトPPAは卒FIT後やFIT制度を適用していない太陽光発電の新たなビジネスモデルとして期待されており、法人向けの制度として注目が集まっています。契約期間や価格設定の柔軟性が高く、事業者のニーズに応じたカスタマイズも可能です。
リパワリングで発電効率を上げる
リパワリングとは、経年劣化した太陽光発電設備の機器を新しい製品に交換することで、発電効率を回復・向上させる方法です。とくに寿命の短いパワーコンディショナー(一般的に10~15年)の交換は、効果的なリパワリング策です。
太陽光パネルの期待寿命が20〜30年であるのに対し、パワーコンディショナーは相対的に寿命が短いため、計画的な交換により発電量の維持・向上が図れます。リパワリングにより発電効率が回復すれば、売電収入の増加だけでなく、中古物件としての資産価値向上も期待できます。

水上太陽光発電で用地の制約を解決する
太陽光発電の設置場所が限られているという課題に対し、注目されている解決策が「水上太陽光発電」です。NEDOの再生可能エネルギー白書によると、日本の「水上空間(湖沼・ダム水面)」の導入可能ポテンシャルは38.8GWと推定されています。
水上太陽光発電の大きな利点は、農業用ため池や貯水池といった既存の水面を活用できる点にあります。これにより、造成工事が不要となり、土地の整地や障害物の除去といった初期投資や工期を大幅に削減できます。
また、水面は樹木などの遮蔽物が少なく、反射光の効果も得られるため発電効率の維持が期待できます。加えて、水面による自然冷却でパネルの温度上昇を抑え、効率低下を防ぐことも可能です。
森林伐採や農地転用といった環境負荷をともなわずに設置できることも大きな利点です。加えて、水面を覆うことで蒸発を抑制し、藻類の異常発生を防ぐ効果も期待されており、水環境の改善にも寄与する可能性があります。
出典:環境省「水上太陽光発電所の現状及び環境影響について 第3回太陽光発電施設等に係る環境影響評価の基本的考え方に関する検討会より」
まとめ
太陽光発電は、売電価格の下落や出力抑制の増加、いわゆる「2030年問題」など、多くの課題に直面しています。とはいえ、技術革新や国の政策支援、そして再生可能エネルギーへの社会的要請の高まりにより、その将来性には依然として大きな期待が寄せられています。
自家消費の拡大、売電先の多様化、設備のリパワリング、そして水上太陽光発電のような新たな設置手法を組み合わせることで、収益性と持続性を高めることが求められます。
シエル・テールは、水上太陽光発電のパイオニアとして世界で初めて水上太陽光発電用の架台システムを開発したフロートメーカーです。10年以上にわたる豊富な実績に裏打ちされた高い信頼性と耐久性を誇り、多様な現場ニーズに応えています。
さらにEPCだけでなく、設備の運用管理を行うオペレーションやマネージメントまで、一貫して自社で行えるため、より納得のいく施工が可能です。太陽光発電システムをご検討中の方は、ぜひシエル・テールにご相談ください。
株式会社シエル・テール・ジャパンの提供するサービスやプロジェクトについてはこちらをご参照ください
BY MIKU, SALES & MARKETING, CIEL TERRE JAPAN







